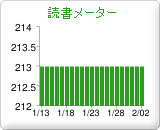『科学者が人間であること』

「私は人間である」と意識する瞬間はどれくらいあるでしょうか?
また、人間はどの位、自然界と絡み合って生きているのでしょうか?
著者の中村さんは生命誌という学術分野の第一人者。さまざまな生物が、共通の祖先から進化しながらDNAをつないできた歴史を明らかにしてきました。このような世界観のなかでは、人間社会のなかにある論理と、自然界の理には大きな隔たりを感じざるを得ません。
そこで、著者が主張しているのは、「重ね描き」ということになります。単に画一的で分析的な見方をするのではなく、自然のなかの生活者として、社会に生きる一人の人間としての見方を重ね合わせ、総合的な感じ方を忘れないということだと、私は理解しました。
先端研究者は皆、職業的に科学者をしているとは私にはむしろ意外なことでした。これまでお会いした研究者の多くは非常に幅広い教養を持っているように感じていたからです。中村さんの求めるように、研究者に限らず、リーダーにはさまざまな視点から世界を見て欲しいですね。
『科学者が人間であること』からの名言
ここでは、科学技術に注目し、研究者に重ね描きを求めてきましたが、日常感覚や思想性を求められるのは研究者に限りません。政治家、官僚、企業人などなどすべての人が、その専門からだけものを見るのではなく、生活者、思想家であることが求められています。
気づいたこと
何ごとも突き詰めると同じような結論になる
今日の一言
科学って人間の役に立つように作られてきたのに、自然科学とはいかに?
| テクニック | |
|---|---|
| マインド | |
| 革新度 | |